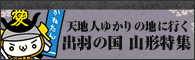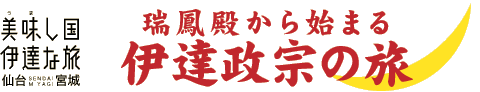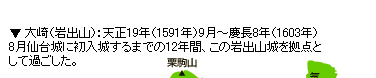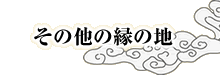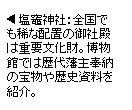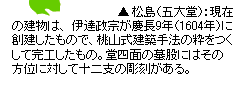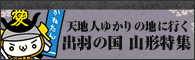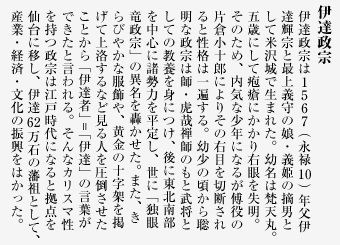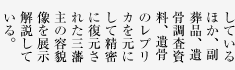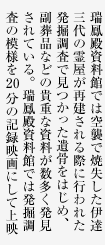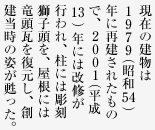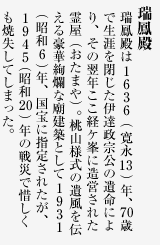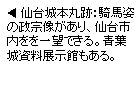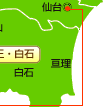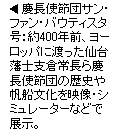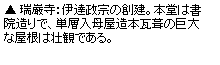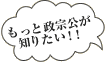わずか6年で南奥羽を次々と攻略し広大な勢力を気付いたが、秀吉の天下統一が確実となったとき、己の若さを恨んだ政宗。秀吉、家康に仕えながらも、地方にあって天下を睨み続けた政宗は、度重なる窮状も、奇抜なアイデアを発揮して切り抜けます。仙台開府後は、神社、大崎八幡宮、国分寺薬師堂、瑞巌寺を建立。また、南蛮貿易を企図し、独自に「奥州王」として使節を派遣。その一方で仙台藩62万石の基盤を確立させた伊達政宗。彼が関った建造物や史跡は、いまも往時を偲ばせ、その功績を伝え紹介する施設も整備・展示されています。「政宗イズム」を見て400年前の仙台に思いを馳せる旅。
 |
 |
 |
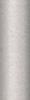 |
|
 和みをテーマにした瑞鳳殿オリジナルのグッズも販売中! 和みをテーマにした瑞鳳殿オリジナルのグッズも販売中!
詳しくはHPにて
http://www.zuihoden.com |

五葉山火縄銃鉄砲隊
青葉まつり出陣式 |
| |

冬の瑞鳳殿 |

秋の瑞鳳殿 |

春の瑞鳳殿 |
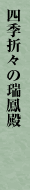
|

新年拝礼式 |

御霊屋までの
美しい階段 |
|
|
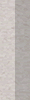 |
 |
 |
 |

亘理城主伊達成実(しげざね)は、伊達政宗の重臣で、幼少の頃より政宗に仕えた。(政宗の従兄弟)成実に子がなかったため、政宗の2男である宗実を養子に迎え代城主とした。
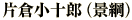
出羽国置賜郡下長井庄宮村(現長井市)で生まれる。父は神官。伊達政宗の父輝宗に認められ、守役として仕える。以来、独眼竜政宗の片腕として常に政宗の側で支えてきた。 |

白石城は白石市の中心部にある益岡公園にあった平山城で、中世末期、地元の士豪白石氏の居城であったが、慶長七年(1602)以降は仙台城の支城として伊達家の重臣片倉氏が代々居城し、元和元年(1615)の一国一城令後も例外的に「城」としての存続が認められた。明治維新時には、白石城で奥羽越列藩同盟が結ばれるなど歴史が大きく転換する時にたびたび登場し、重要な役割を果たしてきたが、その後片倉家は、開拓費用に充てるため白石城の売却を申請し、明治七年以後随時解体された。
白石市民の長年の夢であった白石城の復元は、市民の間から復元の浄財が寄せらわるなど復元に対する運動が起こり、平成七年(1995)に三階櫓(天守閣)と大手門を、史実に忠実に復元された。 |
 |